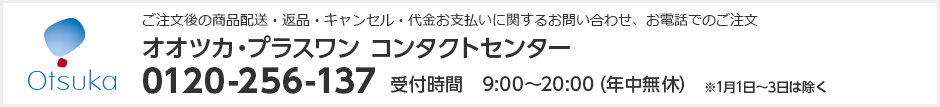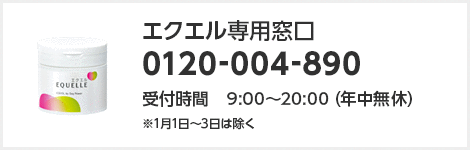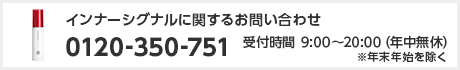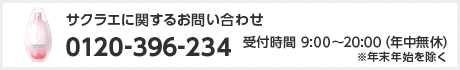健康な生活を送るうえで欠かせない、日々の食事。みなさんは食事をするうえで、どんなことに気をつけていますか?
1日3食、規則正しい食事をとる、ダイエットのためにカロリー制限をする、食べる順番を気にする……。そんなふうに、いろんな工夫を取り入れている人もいれば、「とりあえず、おなかが満たされればOK!」という人もいるかもしれません。
食事は私たちが生きるうえで欠かせないものであり、健康な体づくりを支える大切な習慣です。そんな健やかな食生活のカギを握るとして、いま植物性食品が持つチカラが注目されています。
「健康寿命」を支える毎日の食事

日本は世界でも有数の長寿国。そして、その長寿を支えている理由のひとつが、日本型の食生活だといわれています。一方で、健康上の問題で日常生活が制限されず、自立した生活を送ることができる「健康寿命」と平均寿命の差が問題となっています。健康寿命を支える要素はさまざまですが、食生活もそのひとつ。
そのような中、最近では健康への関心が高い人々を中心に、古くから長寿を支えてきた日本食の良さが再認識されています。また日本食以外でも植物由来の食品を意識して活用する食生活にも注目が集まっています。
従来の日本型食生活と現代の食生活の違いはどこにあるのでしょう。そして、なぜいま植物性の食品が注目されているのでしょうか。詳しくみていきます。
食の欧米化がもたらした食生活の変化

日本人の食生活を語るうえで、「食の欧米化」という言葉がよく使われます。では、食の欧米化とは、具体的にどんなことを指すのでしょうか。
戦後から現代までのあいだに、日本人の食生活はずいぶん様変わりしました。なかでも大きな変化のひとつとして、米や野菜、魚介類が中心だった食事に、肉類を食べる習慣が加わったことがあげられます。
1960年の1年間で国民1人あたり5.2kgに過ぎなかった肉類の供給量は、高度経済成長期を経た2000年には28.8kgと約5.5倍に増加。2020年には33.5kgとなり過去最高を更新しました。肉類以外では、卵が約2.7倍、牛乳・乳製品の供給量は約4倍に増えています。また、家庭での食事も変化して、ご飯に汁物、おかずが3品という「一汁三菜」の和食だけでなく、スパゲティやオムライスといった洋食メニューが登場することが多くなっていきます。
穀類や豆類といった植物由来の食品が主要なタンパク源だった頃と比べると、米や大豆の摂取量が減り、肉類など動物性タンパク質の摂取量が大幅にアップ。植物性食品の多い食生活に代わって、動物性食品をたくさん摂取する食生活へと変化していったのです。そのような食生活のなか、いまあらためて植物性食品が注目されています。
なぜいま植物性食品が注目されているの?

欧米では、菜食主義の生活スタイルを送る人が少なくありません。その背景として、動物愛護や環境保護、健康志向など様々な理由がありますが、健康面では肉類の消費が上がったことによる肥満との関係も考えられそうです。
肥満は体形の変化だけでなく、生活習慣病などの引き金にもなるため軽視できない問題。野菜や穀類などの植物性食品であれば、低脂肪かつ低カロリーな献立になりやすいので、健康を考えて日本型の食事を選ぶ人も少なくないようです。
また、植物は動物のように自分で動くことができません。自由に生存する場所を変えられないからこそ、強い日射しや激しい気温差など過酷な環境でも生き延びられるチカラを持っています。そうした植物のパワーを食事を通して取り入れることで、健康に役立てられるのではと期待されているのです。
例えば、いま話題の乳酸菌もそのひとつ。乳酸菌は生存する場所によって植物性乳酸菌と動物性乳酸菌に大きく分けられます。厳しい環境で生き抜く植物性乳酸菌はとっても丈夫。一方、動物の乳など栄養豊富な場所で育つ動物性乳酸菌は、生きたまま腸まで届きにくい代わりに、植物性乳酸菌のエサとなってその働きをサポートします。
動物性食品と植物性食品はバランスが大事

食事をするうえで、動物性食品と植物性食品をそれぞれ摂取することは重要なことです。
なかでもタンパク質は、私たちが生命を維持するうえで欠かせない重要な栄養素。筋肉や内臓、皮膚、髪などを構成する成分であり、不足すると成長が阻害されたり、体力や免疫力の低下を招いたりしてしまうため、毎日の食事を通して意識して摂取しなければなりません。
タンパク質も乳酸菌のように、動物性のものと植物性のものに大きく分けられます。動物性タンパク質は肉類や魚介類、卵、乳製品などの動物性食品に、植物性タンパク質は豆類や穀類などの植物性食品に多く含まれます。どちらもタンパク質ですが、それを作っているアミノ酸の種類や量が異なるので、健康を保つうえでは両方をバランスよくとることが大切です。同じタンパク質だからといって、どちらか片方に偏ってとることはおすすめしません。
植物性タンパク質を代表する「大豆」のチカラ

植物性食品のなかでも、特に注目したいのが大豆です。大豆は別名「畑の肉」とも呼ばれるほど、すぐれた栄養価を持つ植物性食品。体のなかで合成することができない必須アミノ酸をバランスよく含んでいます。
タンパク質の栄養価を評価するときに、「アミノ酸スコア」という方法が用いられますが、大豆のアミノ酸スコアは肉や魚、卵と同じく最高点の“100”。動物性タンパク質に比べてカロリーが低いのも大きなメリットです。
植物性食品のチカラを上手に取り入れるには?

丼ぶりや焼きそばなどの一品物だと、どうしても栄養バランスが偏りがちに。植物性食品の摂取量も少なくなってしまいます。
無理なく植物性食品を摂取するなら、やはりオススメは一汁三菜の和定食。白米などの主食に、肉類や魚介類、卵、大豆などのタンパク質がメインとなった主菜、野菜やキノコ、海藻などを使った副菜と汁物を組み合わせた献立が理想です。
ただし、従来の和食では塩分をとりすぎてしまうことがあるのでご注意を。ダシの風味を活かしたり、フレッシュな旬の食材を活用したりして、塩分でごまかさずに素材の持ち味を活かした調理法を工夫したいですね。すべてを薄味にするのではなく、1品だけはっきりした味つけにすれば、メリハリが出て食事の満足度もアップします。
大豆のチカラが詰まった
「ソイジョイ プラントベースシリーズ」
普段の食事だけで植物性食品を補うのが難しい場合は、間食を利用するのもよい方法です。大塚製薬が販売する「ソイジョイ プラントベースシリーズ」も、そんな植物のチカラを活用した食品のひとつ。まるごとの大豆を粉にして焼きあげているので、1本25gで植物性タンパク質6gをはじめ、大豆イソフラボン、食物繊維など大豆の栄養を美味しくスマートに摂ることができます。

ソイジョイ プラントベースシリーズには、卵、乳といった動物性の原材料は一切使用されていません※1。
また、NPO法人べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証※2を取得しています。
低GI食品なので、糖質が気になる方にもぴったり。ちょっとお腹が空いた時のお供に、ソイジョイ プラントベースシリーズをご活用ください。
※1ただし、卵、乳、ピーナッツを使った製品と同じ設備で製造しています。
※2原材料として、肉・魚介類・卵・乳製品・はちみつ等、
動物に由来する物質を含まないことが確認できたものに対し、付与されます。
- 参考
- 大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A|農林水産省
- 健康寿命とはどのようなもの?|公益財団法人生命保険文化センター
- 栄養面から見た日本的特質|農林水産省
- 日本の伝統的食文化としての和食|農林水産省
- 日本人の食事をめぐる状況と「健康な食事」のあり方|厚生労働省(PDF)
- たんぱく質|農林水産省
- たんぱく質|e-ヘルスネット
- 植物性たん白とは?|一般社団法人日本食物蛋白食品協会
- 栄養に関する基礎知識|国立循環器病研究センター循環器病情報サービス
- 食品たんぱく質の栄養価としての「アミノ酸スコア」|日本食品分析センター(PDF)
- 数値からみた食生活の変化 国民健康・栄養調査に基づいて|御茶ノ水大学(PDF)
- 食料需給表|農林水産省


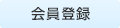
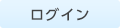





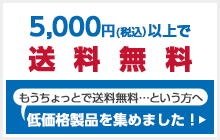
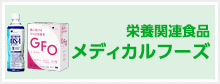
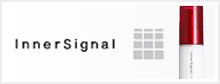
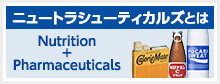

 Amazon.co.jp にご登録のクレジットカード情報を利用してお支払いいただけます。
Amazon.co.jp にご登録のクレジットカード情報を利用してお支払いいただけます。 GMOペイメントサービス株式会社の提供する「GMO後払いサービス」がご利用いただけます。
GMOペイメントサービス株式会社の提供する「GMO後払いサービス」がご利用いただけます。